前回の続きです。
基礎問題で出題の多い領域
連続波ドプラ法
- 高速血流の検出に優れているか
- 指向性のないプローブを使うか
- 送信と受信の素子が異なるか
- 角度補正(調整)は不要か
- エイリアシングにならないか
- 距離分解能あるか
- 方位分解能あるか
高調波
- 高調波は減衰しやすいか
- ティッシュハーモニックは高調波を使うか
- 高調波の発生について
- 造影剤はティッシュハーモニックイメージング。
- 基本周波数は関係ないか
- 音圧が高いほど高調波得られやすいか
- 非線形性により高調波が発生するか
- 伝搬する過程が長いほど高調波得られやすいか
高調波に関しては『そうなんだ、よく出題されてるんだ』というのが正直な感想です(恥)新たな発見が出来ました。
MI/TI
- TIの値で気をつけるのは
- MIは生体内での機械指標か
- MIに関わるのは(負の音圧ピーク、中心周波数)
- MIは生体内の熱的作用に関与するか
- TIは熱作用に関与するか
- TIは音響パワーより求められるか
- MI単位は何か
- TIはキャビテーションの原因になるか
- MIは周波数に依存するか
- TIについて(温度上昇)
距離分解能
- 距離分解能の良いパルス波を図から選ぶ
- プローブ固有である
- 周波数に依存しない
- 距離分解能を向上させる方法(送信パルス幅の設定を変える)
カラードプラ法
- パルスドプラよりフレームレートが落ちるか
- Bモードより出力パワーが大きいか
- 距離分解能は低下するか
以上が良く出題されるようです。納得だったり以外だったり。皆さんはどう感じられたでしょうか。
個人的によく目にした問題
3回基礎を受けて「あ、この問題よくみるな」と感じた問題も書かせていただきます。
- コメット様エコーの写真問題(何のアーチファクトか選択)
- フォーカスを合わせる時の素子駆動タイミング
- 媒質の実際の厚さを求める
- 患者漏れ電流について
- 患者装着部の型別分類
- 減衰について
- 単一故障について
- ウォールフィルタについて
- STCについて
今年度超音波専門医基礎問題について
受験された医師から出題問題を教えて下さいました。
(※専門医合格されたそうです。おめでとうございます!)
- ドプラ偏位周波数を求める
- 反射係数の問題
- 実測距離を求める
- 波長を求める
- 視野深度を求める
- アーチファクトとその現象を結びつける
- 後方散乱について
- パワードプラについて(カラードプラよりも出力大きい/エイリアシング起こらない)
- 帯域幅について
- 方位分解能を上げる方法
- パルスドプラ波形で縦軸と横軸はそれぞれ何を表示してるか
- 剪断波で硬さの計測は可能か
- 音波の縦波・横波について
- ドプラ効果について(観測者が円を描いて移動し、音源が円中心の際ドプラ偏移周波数は正・負・ゼロどれか)
- MIとTIについて
- STC
- 患者装着部の分類
- 物質の音速について
- 検査時の環境について
出題傾向が比較的似ているように思うのは私だけでしょうか…突拍子もない問題は出ていなさそうですよね。
今回問題をまとめていてやはり基礎って大事だよな、面白いなと改めて感じました。
今後も超音波基礎について書かせていただこうと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
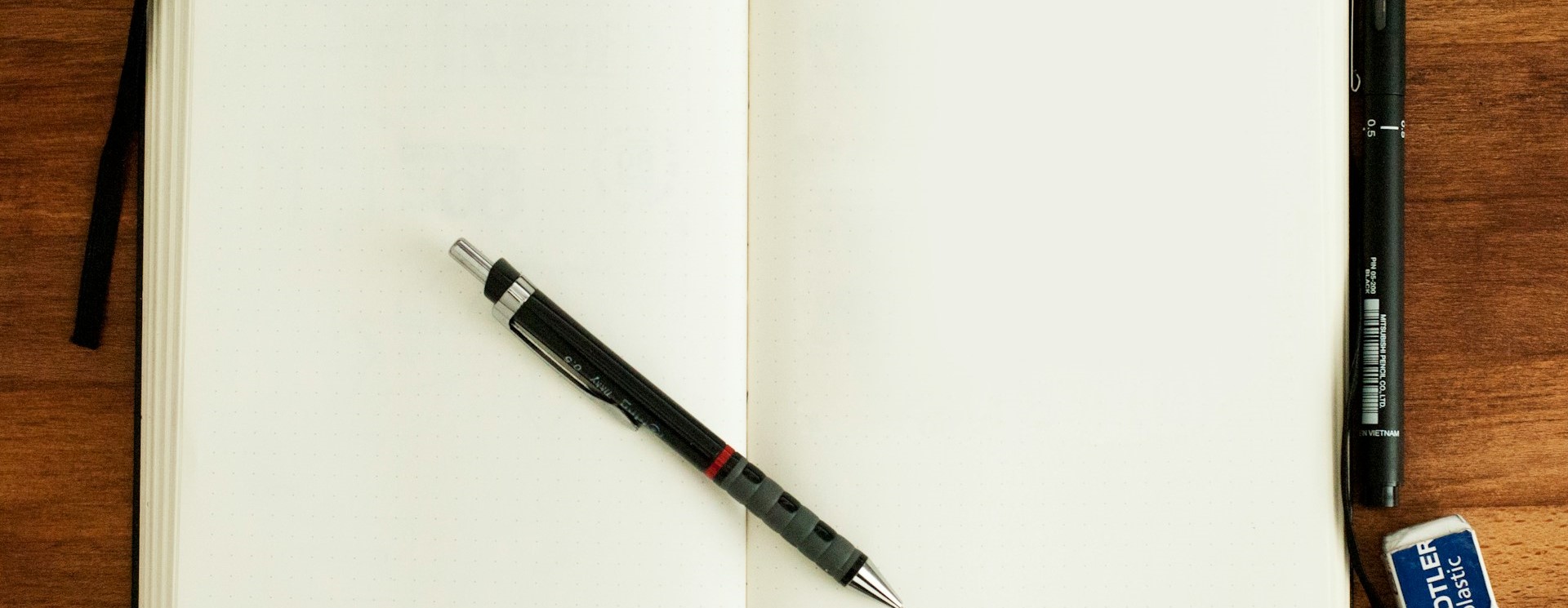

コメント