お疲れ様です。
先日こちらに書かせていただいた医師から超音波専門医基礎の出題問題を教えて下さった際、超音波検査士基礎で出題の多い問題って何だろう…?と疑問に思いました。
過去問をまとめてみると興味深い結果だったので書かせていただきます。
基礎問題で出題の多い領域
- 診断装置
- プローブ
- フレームレート
- エイリアシング
- 電源の容量
- 連続波ドプラ法
- 高調波
- MI/TI
- 距離分解能
- カラードプラ法
ネットやSNS、私が過去に受験した際に書き留めた内容で集計すると、こちらの10項目がよく出題されているようでした。
今回は1.~5.まで、具体的な問題も含めて書かせていただきます。
装置診断
普段エコー機を扱っているソノグラファーにとって、サービス問題のようなものですよね。
- エコーゼリーの役割
- エコー機ディスプレイの清掃方法
- ゲインは出荷時に最適にされているので触らない
- 日常点検について
などが出題されていたようです。
プローブ
こちらもソノグラファーには嬉しい。でも構造に関しては日々考えながら業務している方は少ないと思います。
- 滅菌方法はオートクレーブか否か
- プローブを使用しない時でもエコーゼリーはつけたままにしておくのはNGか
- プローブコードを曲げるのはNGか
- プローブ表面のひび割れはNGか
といったプローブ取扱いに関する問題や、
- 音響レンズは生体より音速が速いか
- バッキング材は帯域幅を広くするか
- 音響整合層は生体と振動子の反射を少なくする役割があるか
といった構造に関する問題、
- アレイプローブ、圧電振動子
- コンベックスプローブはどのようにビームが出ているか
- コンベックスプローブは多段フォーカス可能か
- リニアプローブはグレーティングローブがあるか
- 全振動子を駆動させるには
- 振動などの機械作用で熱を帯びるか
等が出題されていたようです。
フレームレート
- フレームレートを上げるには
表現を変えつつ、こちらの問題がよく出題されていたようです。
私自身も受験した際よく見た記憶があります。
エイリアシング
- エイリアシング回避の方法
こちらもよく見かけました。ルーチンでもよく遭遇するので原理を知っておくことは必要ですよね。
電源の容量
- 〇〇A、〇〇〇V機械を〇〇〇Wだと何台繋げることが可能か
計算を覚えておけばこちらもサービス問題ですね。
中間まとめ
装置やプローブは色々な種類の問題が出題されているのかな…
受験時はそのような印象がありませんでした(恥)
6.~10.は次回書かせていただきますm(__)m
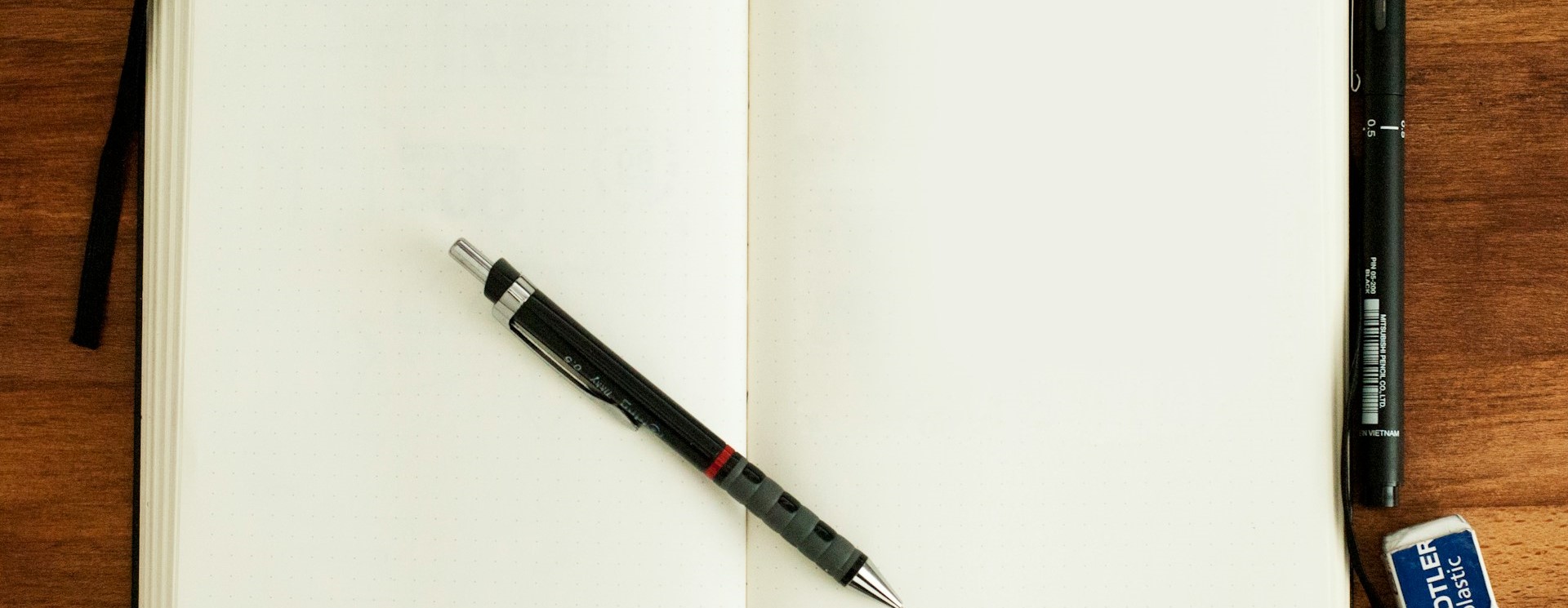

コメント